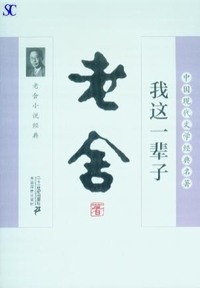魯迅の代表的な著作の一つ。中国における小説文化の歴史についてまとめている。テキストのもとになったのは大学での魯迅の講義プリントである。
中国文学史を深く学びたいなら是非とも読むべき一冊。とはいえ一般向けではないので予備知識も無しに読むと理解の及ばぬ部分も多い。ネットを見回しても本作をきちんと紹介しているサイトが全然見当たらないので、これから史略を読みたいという方向けに色々書いていこうと思う。
まず、本作の生まれた経緯から説明したい。近代以前の中国において、小説は長らく庶民の低俗な娯楽だった。現代人の感覚で置き換えるなら、2チャンネルのスレッドやSS小説あたりといったところだろうか。暇潰しにはいいけれど、形にして保存するようなものではないし、誰も深く読み込んで考察などしない、そんな代物だったわけ。
何故小説が低俗とされたのか。理由は色々あるけれど代表的なものを下記にあげる。
・嘘が多いこと。小説はそもそもが荒唐無稽な内容を多く含む。孔子が「怪力乱神を語らず」と述べたように、元来中国の教養人はオカルトチックな話を信じるのはよくないこととされていた。
・儒教礼儀に背く内容が含まれること。自由恋愛や不倫、殺人や反乱など、人々を面白がらせる話というのは大体背徳的な内容に陥りやすい。中国において学問は聖人の道であり、これらの道徳を無視した物語は当然排除されるべきものだった。特に民間発祥の小説は、為政者にとって都合の悪い内容を含んでいることも多々あったので、禁書の対象にもなりやすかった。
けれども、上記の低俗云々は、あくまで文人層の話。庶民の間では主に唐代以降、講釈師の語りを通して小説文化が広まっていった。学問をしない彼らからすると、聖人の教えやら礼儀云々はどうでもいいので、倫理道徳スレスレの下世話な物語も普通に楽しむことが出来たわけである。現象としては、教養人達や表現規制派が「テレビ番組を見たらバカになる」「ゲームをする人間は犯罪者になる」「○○という人気漫画は教育や倫理的によくない」と突っかかっていくのと似たようなもの。エンタメに関して人間の言うことなんて今も昔も変わらないのだ。
中国の歴代王朝は禁書という対応で度々小説を弾圧したが、それでも庶民の需要を止めるまでには至らず、書店や講釈師も検閲の目をくぐり抜けたので、小説はどんどん浸透していった。中国の文学史をわかりやすく表したフレーズに「漢文唐詩宋詞元曲明清小説」というものがあるが、明清に至って小説は文化の最盛期に至った。印刷技術の発展や書店の流通、そして本来小説を蔑んでいた文人層の中にも小説にドハマリする変わり者がいて、自ら傑作を書き上げたり、書評をしたりするほどになっていた。それでも、表向き小説の文化的地位は相変わらず低いままだった。
しかし、その状況が一変する事件が起きる。西欧列強による中国侵略である。中国の知識人達は、度重なる敗北によって自らの国に欠けているものが何かを考えるようになった。軍事、政治、文化……それらを模索するうちに、何人かの知識人達は、西欧における小説文化が自国と決定的な違いを持っていることに気がついた。西洋では、小説が芸術的な価値を持って人々に受け入れられ、かつ庶民を啓蒙するメディアとしての役割を担っていた(ここらの詳細を語ると長くなるので、気になる方は岩波文庫の「梁啓超文集」に掲載されている「小説と群治の関係」を参照されたし)。
かくして、中国人の小説に対する見方も大きく変わった。小説を使えば、大衆を感化させ意識改革を起こすことが出来ると考えたわけである。幾人かの中国人(主にジャーナリストや雑誌編集者が多かった)は、西洋人の悪辣さや政府の腐敗を糾弾する政治小説を大量に書くようになった。また知識人層は西洋の小説を翻訳したり、自国の小説について研究を始めた。
こうした小説に関する認知の変化は、1910年代の文学革命に発展した。即ち、大衆が慣れ親しんでいる小説文化を改革して、大衆の意識を変え近代的な発展を目指そうというものである。魯迅もまたその一人であった。もともと医者を志していた彼は、西欧列強に侵略されながらも奴隷根性で生き続けている中国庶民を目にして、彼らを癒やすのに必要なのは「体を治す薬」ではなく「心を治す薬」だと考えた。その薬というのが即ち、文学だったわけである。文人達ははじめ西洋文学の模倣をしつつ、後にオリジナリティも加えた小説を書き、近代の中国文壇を形成していった。
こうした文学運動の一環として、自国の小説文化の見直しは必須であった。梁啓超のように、旧来の小説にはろくなものが無いから中国人民が堕落するのだ、と考える者もいれば、王国維のように自国の小説にも「紅楼夢」を筆頭に西洋文学に相当する作品があると主張する者もいた。
ところが、小説研究の中で大きな問題があった。小説文化は長らく低俗なものだったので、研究しようにも文学史をきちんとまとめた書物が存在していなかったのだ。一応、過去にも王朝の命令で目録が作られたり、物好きな文人によって残された記録が多少はあったりしたものの、小説を一つの芸術文化として認識し、体系的にまとめたものは無かった。
そこで魯迅が自らの大学講義をもとに作り上げたのが、この中国古典小説史略、というわけである。
前置きが大変長くなってしまったが、本作の歴史的な価値は主に二つある。
一つは、小説の変遷についてわかりやすくまとめたこと。「小説」という言葉自体はかなり古い時代の書物から存在していた。当然ながら今日の小説とは意味が異なり、正史に含まれぬ野史の分野を専門とする諸子百家の一派だった。魯迅は歴史の記録上に残された小説という言葉を時代ごとに取り上げ、その意味の変遷をわかりやすく本作で述べている。それにより、古代から近代まで、小説が文学上どのような立ち位置を持ち、またどのように発展してきたかが明確になった。
これはちょっと思い出話になるのだけれど、私が大学で中国文学の専門講義に触れた時、まず最初に語られたのが「小説」という言葉の分解だった。つまり魯迅が述べていることと同じで、古い文献の「小説」がいかにして現代と同義の「小説」になったか教えてもらったわけ。専門的な文学講義に初めて触れた私にはとても新鮮な内容だったけど、後々史略を読んでなるほど文学史では基本的な考え方だったのかと改めて唸らされたりもした。
話を戻すと、多くの中国知識人が旧来の小説をけなすか持ち上げるかで躍起になっていた中、魯迅のアプローチはまさに独自のものであり、かつ学術的にも非常に有益だった。実は魯迅以外にも中国小説の通史を作成した研究者が同時代にいたのだけれど、結局魯迅の史略ほど浸透しなかったのは、小説でないものを小説扱いして通史に含んでいたり、そもそも各時代の内容が半端だったり、魯迅ほど内容が一貫していなかったためと思われる。
二つには、主に唐代以降に生まれた小説について細かくジャンルを分類したこと。過去の時代にも王朝の目録などで大雑把な分類はされていたのだが、何せ小説なんて真面目に記録する類のものではないから、ジャンル分けも非常にいい加減だった(明らかに小説でない本が小説として分類されていたり、その逆もしかり)。魯迅は各時代の代表的な小説について読み込み、さらに自ら神魔、狭邪、譴責などジャンル名を作りわかりやすく分類した。魯迅の命名した分類は今日の中国小説研究でも使われており、まさに歴史に残る偉業といえる。
さて、ここまで述べた通り、本作の生まれた経緯にはかなり歴史的な事情が関わっているので、一般向けの本とは言い難い。中国文学をある程度読んでおり、そのうえでさらに深く知りたい、あるいは文学研究をしたいといった段階になって手に取るレベルの本である。
また、研究書として読むにしても留意しておかなければならない点は幾つもある。第一に百年も前の著作なので、内容の多くは現代の文学研究でかなり更新されている。そのまま鵜呑みにして「中国小説史略にはこう書いてあったからその内容が正しい!」なんて言ったらとんだ恥をかくので注意しよう。本作で紹介されている作品については、四大名著はもちろんのこと、マイナーどころのタイトルについても、興味があるなら最新の研究本をあたった方がいい。
さらに言うと、本作はそもそもネットも無ければ資料も存分に集められなかった時代の研究書なうえに、魯迅も手元にあった小説を全て読み込んでいたわけでは無く(何せ清代あたりになると小説ブームのせいで、有名作品の偽物や模倣や二次創作、作者の自己満足を詰め込んだゴミみたいな作品も書かれたりしてたので、魯迅もあまりのつまらなさに投げ出してしまった物もあったそう。また、清末でブームになった譴責小説は政治的内容や作者の強烈な主張が強すぎて物語になっていない作品も多かった)、さらに元ネタが講義内容の繋ぎ合わせであり説明に乏しい部分もある。膨大な注釈を見ればそれがよくわかるだろう。
もし中国小説の通史を知りたい、ということであれば日本の中国研究者がさらにわかりやすい本を幾つか出している。個別の作品について読みたいのであればガイド本をあたってほしいが、生憎日本だとまだまだ一般向けに中国古典小説をわかりやすく紹介したものは少ないのが残念なところ…。ちなみに中国小説史略で紹介されている小説作品は大体翻訳がある。
中国小説史研究書の元祖として、本作の歴史的な地位は今後も決して揺るがないと思う。
ディープに中国小説を楽しみたい方は是非読むべし。翻訳は複数出ているが、個人的には東洋文庫のものがお勧め。お値段は高いけれど、文庫サイズで持ち運びも便利。